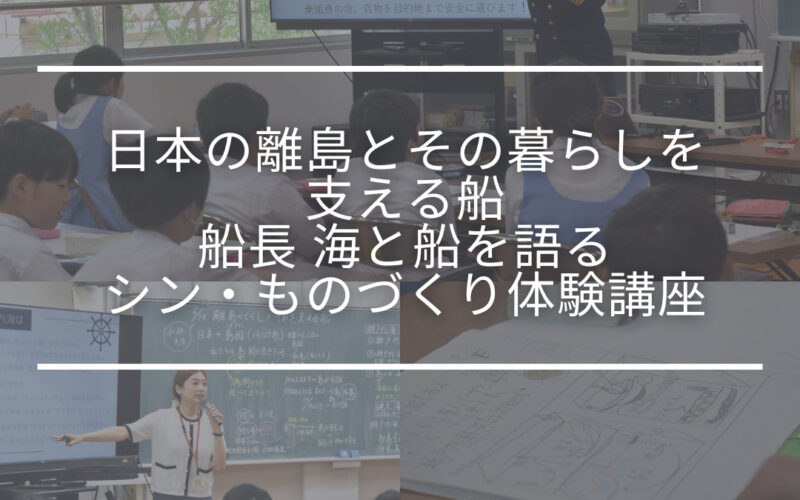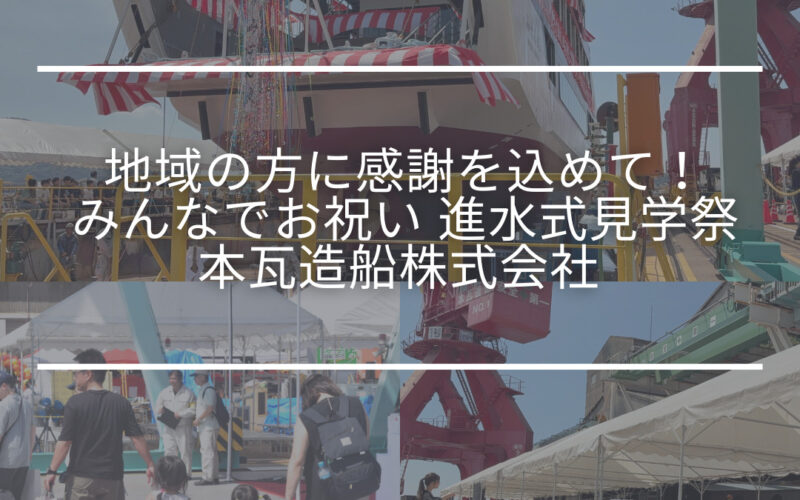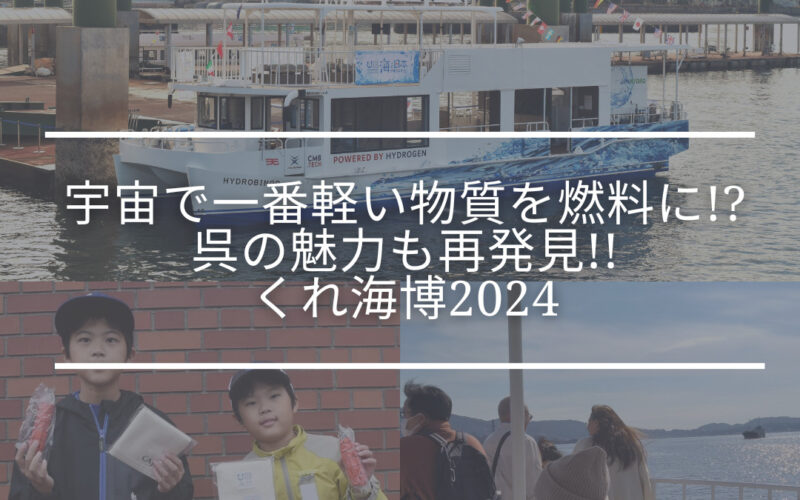TFC進水式・アスンシオン大学 交流会|ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社

オールジャパンで
海を未来へ引き継ごう
海と日本PROJECTは日本財団、総合海洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、オールジャパンで推進するプロジェクトです。私たちを支えてくれる海の現状を伝え海を未来へつないでいくためのアクションの輪を日本全国に広げていきます。今年は特に猛暑といわれています。熱中症対策をして、海を安全に楽しみましょう。

今回の記事では2025年7月9日に尾道市立浦崎小学校を招待し、ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社で行われた、進水式見学会とアスンシオン大学交流会の様子をご紹介します。
会場の様子
式典会場は広島県福山市に本社を置く、ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社です。

式典の装飾やリハーサル、安全対策などの準備が順調に進む中、尾道市立浦崎小学校の生徒たちも到着し、いよいよ進水式のスタートです!




子どもたちは工場内の船に興味津々!ワクワクしながら会場へ!
進水式

進水していく船はとても迫力があり、子どもたちも大興奮でした。軽くて鉄と同等の強度があるアルミニウム合金を使って速度の出る船を建造するのがツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社の特徴です。
進水した船をバックに記念撮影を行う際に、ドックの設備も見学できました。


生徒の感想
船体についているくす玉がすごかった。
支綱切断がかっこよかった。
くす玉が完璧なタイミングで割れていた。
小さいころに見たことがあったんですが、改めて見てすごいなと思いました。
アスンシオン国立大学 交流会

進水式の後はパラグアイから来日された講師の方々との交流会です。パラグアイってどこにあるか知っていますか?日本のほぼ真裏にある国なんです。国土は日本の1.1倍、人口はおよそ800万人、日本からパラグアイの首都アスンシオンに行くには航空機を利用して約2.5日かかります。60年前、日本人がパラグアイに行ったときは船での移動だったので1か月以上かかっていました。
質問コーナー
パラグアイはどんな国ですか?
移民が集まった国で、いろんな国の人がいます。気候は日本と同じように夏は暑いのですが冬が1週間ほどしかないので夏が長い国です。内陸なので海がなく、水遊びは川に行きます。
パラグアイの料理を教えてください
日本ではお肉を少しずつ食べ、お米を食べるかと思いますが、パラグアイはその逆でお肉が主食でパンを少し食べます。農業国ですので、どこに行っても牛がいます。
パラグアイの有名な食品を教えてください
野菜がたくさんあります。その中でもキャッサバが有名です。パラグアイではキャッサバのことをマンジョッカと呼ばれています。
講師メッセージ
先生方の子どもの頃の夢と、なぜ今も研究をされているのか教えてください。
Dario Alberto Alviso(ダリオ アルベルト アルビソ)
子どもの頃は、軍人だった父の影響で自分も軍人になりたいと思っていました。でも、父が軍の技術部門で働いていたことを知ってからは、次第に技術系の研究者に興味を持つようになりました。 今の仕事の魅力は、世界中のさまざまな国や地域を訪れ、現地の文化に触れながら多くの人と交流できることです。そうした経験を通じて、新しい知識や視点を得られるのがとても貴重だと感じています。
Primo Antonio Cano(プリモ アントニオ カノ)
パラグアイには豊富な地下水があります。父は「ボーリング」と呼ばれる地下水をくみ上げるための穴を掘る仕事をしていて、その影響で私は幼い頃から機械に囲まれて育ちました。 大学に進学する頃には、自然と機械工学の道を志すようになり、現在はアスンシオン国立大学で教壇に立ちながら、ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社と協力して水素に関する研究に取り組んでいます。こうして自分の専門分野で実践的な研究ができることを、とても嬉しく思っています
Jorge Hiroshi Kurita(ホルヘ ヒロシ クリタ)
私は子どもの頃から打ち上げ花火が大好きでした。パラグアイでは打ち上げ花火が手に入らなかったため、自分で調べて、独学で作ったこともあります。(※危険なので絶対に真似しないでください)その経験がきっかけで、いつかロケットも作ってみたいという夢を持つようになりました。けれど、パラグアイにはロケット工学を学べる環境がなかったため、大学時代にアメリカへ留学しました。そこで、NASAの研究員と一緒に研究する貴重な機会を得ることができました。 夢は努力すれば必ず叶います。皆さんも勉強を続けて、チャンスがあればぜひ海外に飛び出してみてください。
造船所に足を運び、実際に進水式を見学することで、SNSや動画だけでは味わえない特別な体験を得られたのではないでしょうか?会場の雰囲気、来賓の方々の緊張感、そして現場作業員の熱意が交錯し、多くの人々の思いが詰まった素晴らしい進水式見学会でした。
この見学会を通して、多くの子どもたちに海事産業の世界を知ってもらい、船に携わる仕事を将来の選択肢の一つとして考えてもらえると嬉しく思います。
また、パラグアイからお越しいただいた先生方と交流し、日本とは異なる文化に触れることによって今まで見えていなかった世界が開かれたのではないでしょうか。しっかり勉強をして、いつかパラグアイの大学の先生に会えるといいですね。
進水式に関する情報は各造船所の公式ホームページに掲載されていますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。一般の方でも参加可能な進水式もありますよ!
今後もどんどん情報発信していきますので、CAJS特設ページをぜひご覧ください!!
船舶専門集合サイト フネコネは、有限会社小林船舶設計が運営しております。
この特設ページでは、一般社団法人日本中小型造船工業会が日本財団から支援を受けて実施している「海と日本PROJECT」の活動やSNS情報などを中心に発信していきます。